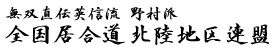居合道は、戦国時代に林崎甚助が始祖されたと言われる武道です。
江戸時代には数多くの流派が生まれ、林崎甚助から七代目の長谷川英信が「無双直伝英信流」を開きました。

明治27年、金沢市に生まれた野村條吉は、第十八代目の穂岐山波雄より「無双直伝英信流」を伝授し、昭和9年頃から、「無双直伝英信流居合道」の指導育成に当たりました(野村派)。昭和33年北陸地区連盟を結成し、昭和51年に「全国居合道連盟」に加入しました。
剣道は、剣道着・袴に防具を付け、竹刀を持ちます。居合道も道着・袴は着用しますが、防具はありません。また、竹刀ではなく摸擬刀(上級者は日本刀の真剣)を持ちます。
居合道は、剣道のようにお互いを激しく打ち合う武道ではなく、一人で仮想の敵を想定し、様々な技術を演武する武道です。そのため、年齢・性別を問わず学べる武道です。
座っている時、歩行している時、鞘から刀剣を抜打ち、斬り付け、納刀にいたるまでの一連の様々な想定を技に込めた武道。想定は、前に・後ろに・左右になどあらゆる場面を空間に想いえがき刀剣を鞘から抜き放ち、斬り、納刀し残心を込める。また、所作を重要視し、礼儀作法にはじまり、刀剣の扱い・手の内など厳しく所見する。